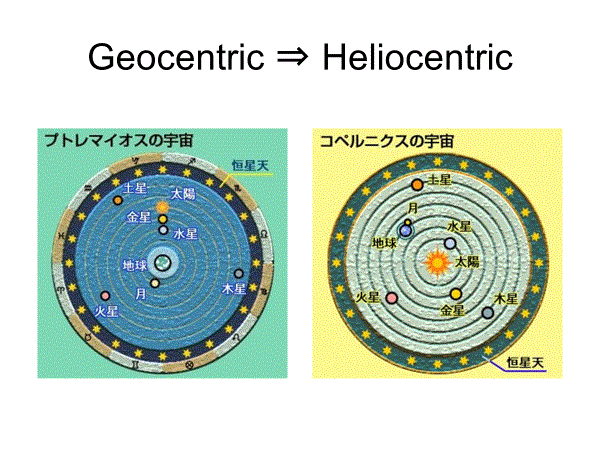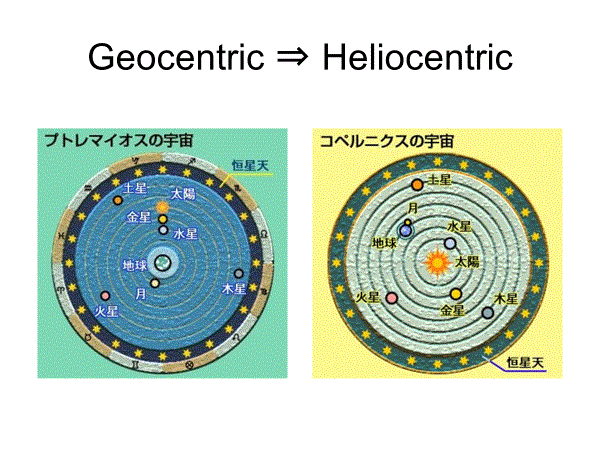■アリスタルコスの地動説(その4)
アリスタルコスは紀元前310-320年ごろ、地動説(太陽中心説)を提唱した科学者である。アリストテレスやプトレマイオスなど大勢の科学者は天動説に与していた。すなわち、古代ギリシャでは、惑星は地球の周りを等速円運動すると考えられた(地球中心体系・天動説) 。古代ギリシャの人々は固定円上の回転円を使って惑星の軌道を説明した(周転円説・エピサイクル).神の創造した世界は完全な調和の世界であり,完全なる図形である円こそが神の世界にふさわしいとされたのである
ようやく16世紀になって、天動説はコペルニクスの地動説に置き換えられた。ガリレオによる木星の周りをまわる衛星の発見や火星の軌道の観測記録から導かれたケプラーの法則、そしてニュートンの重力理論によるケプラーの法則の説明に至る紆余曲折の歴史を経なけらばならなかったのである。
それらを考慮すると、コペルニクスよりも2000年も前に「宇宙の中心は太陽で、地球は太陽の周りを回っている」とする説を唱えたことは、驚愕に値するだろうと思う。
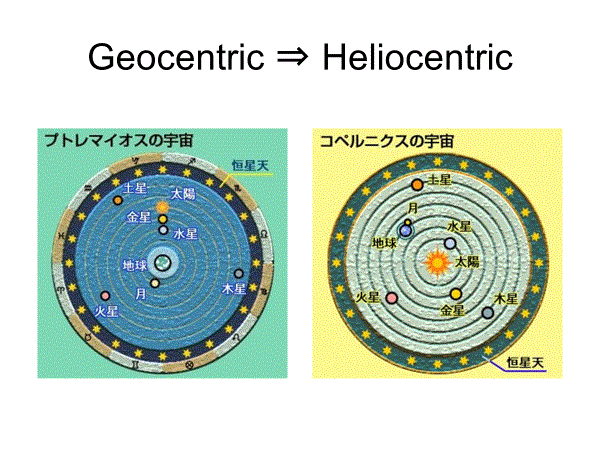
=================================
近代自然科学は一般にコペルニクスの「天球の回転」(1543年) に始まるとされる。それまで支配的であったプトレマイオスの天動説は地球を中心とする回転であり、天球の回転は完全な円運動と考えるものであった。しかし、惑星の運行を円運動としたのでは観測結果と合致しない。それゆえ、惑星の運動は誘導円と周転円との複雑な組み合わせとして説明しなければならなかった。
コペルニクスも天球の運動は円運動であるという伝統的解釈を踏襲したが、それでも天球は太陽を中心として回転するとみることによって周転円の数を著しく減少しうることを発見したわけである。
コペルニクスの地動説は当時の教会の教義に違反するのを避けるため、便利な仮説であるという立場をとったので、当面、法王庁の禁書目録に載せられなかった。しかし、その支持者が次第に多くなった1615年(刊行後60年)、法王庁の禁書目録に載せられることになった。
「天球の回転」には地球が運動していることの直接的な証明はなかった。地球の公転はブラッドレーの光行差の発見(1727),自転はフーコーの振り子の実験(1851)を待たなければならなかった。
=================================
コペルニクスの地動説はケプラーという有力な支持者を見出した。彼はティコ・ブラーエの観測結果を利用して見事な法則を発見した。
1)惑星の軌道は太陽を焦点とする楕円を描く
2)惑星と太陽を結ぶ線分は等しい時間に等しい面積を掃過する
3)惑星の公転周期の2乗は太陽からの平均距離の3乗に比例する
第1法則は完全な円運動でなければならないという伝統的な思考を打破したことで、それだけで画期的な意義を持つものであった。
=================================
ガリレオ・ガリレイは地動説を信奉したため、宗教裁判にかけられた話はよく知られている。彼は望遠鏡を用いて木星の周りをまわる4つ衛星を発見したり土星の輪を観測したという実験的な天文学的業績のほかに、慣性の法則や落体の法則のような地上における力学の法則を見出した。ガリレイは宇宙の法則は数学の言葉で書かれており、その文字は三角形や円などの幾何学的な図形である・・・すなわち、幾何学がなければ宇宙を理解することはできないという有名な言葉を残している
=================================